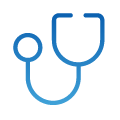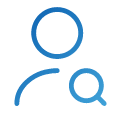院内検査項目説明一覧
/ 中央検査科
院内検査項目説明一覧
当院で行われている検査項目のうちで代表的なものの基準値と意義についてまとめた 一覧表です。
一覧表については各外来でも配布しております。
検査に関するQ&A
採血に関するQ&A
Q
採血をする前に「アルコール綿での消毒は大丈夫ですか?」と聞かれますがなぜですか?
A
アルコールに対するアレルギー等がある患者さんがいらっしゃいますので、全員の方にお聞きしています。以前アルコール消毒で皮膚が赤くなるなどの症状のあった方は、事前にお申し出ください。他の消毒液を使用し対処させていただきます。
また、消毒綿を止めておく為のテープでかぶれたりする方も遠慮なくお申し出ください。
Q
採血後に針を刺したところが青くなってしまいました。どうすればよいでしょうか?
A
針を刺した部分が内出血したために、青くなったものと考えられます。採血後の止血(押え)が不十分なためにおこったと考えられます(血液が止まりにくい、点滴・採血等を頻回に行う患者さんは止血帯の使用をお勧めします)。青みは次第に黄色っぽくなり、1~4週間で元に戻ります。痛みがひどい、青みが広がる、手の先がしびれるなどの症状がある場合はご相談ください。
Q
採血の時、何本もの試験管に分けて血液を入れているのはなぜですか?
A
血液検査をするときは検査項目によって、血液を固めてから上澄み(血清)を検査する場合や、固めないで上澄み(血漿)を検査する場合または固めないで血液をそのまま検査する場合があります。採血管にはそれぞれいろいろな薬剤が入っていて、検査の内容により使用する採血管が違ってきます。
検体検査に関するQ&A
血液の検査に関するもの
Q
偽性血小板減少症とは何ですか?
A
血算検査の採血管にはEDTAという抗凝固剤が入っていますが、このEDTAに反応して血小板が凝集してしまうことがあります。すると機器は凝集した血小板を血小板とは認識せず、実際の血小板数よりも少なく測定されてしまいます。このような現象を「EDTA依存性偽性血小板減少症」といいます。もちろんこれは病気ではありません。このような場合、抗凝固剤がEDTAではない採血管を使用すれば、正しい血小板数が測定できます。
Q
同じ日に複数の科を受診したとき、2回採血をしました。1回目に採った血液で検査をしてもらえないのでしょうか?
A
追加検査があった場合は、先に採血した血液の残量や採血管の種類をお調べした上で、血液量が不足している場合や採血管が異なる場合は再度、採血をお願いしています。
Q
採血のある日に食事をしてきてもいいですか?
A
食事により影響を受ける検査はいくつかあります(下記参照)が特に空腹時採血を指定しない場合もありますので、受診した際に医師の指示をご確認ください。
食事をしないで採血することになっている日にお食事をされてきてしまった時は、必ず診療科にお申し出ください。
食事により高くなる主な項目
血糖、中性脂肪、インスリン、アンモニア(高蛋白食の場合)
食事により低くなる主な項目
遊離脂肪酸
Q
飲酒は検査結果に影響しますか?
A
アルコール摂取直後は尿酸や乳酸が高くなります。また、習慣的にアルコールを摂取している方はγ-GTPや中性脂肪が高くなります。しかし、いずれも個人差があります。
尿の検査に関するもの
Q
尿検査で採尿したら、尿量が少ないのでもう一度取ってくださいと言われました。水分はどんな種類の飲み物をとればいいの?
A
コーヒーや甘い飲み物は糖分が含まれているため、またペットボトルのお茶は防腐剤としてビタミンCが含まれているため、検査結果に影響が出ることがあります。できれば何も含まれていないミネラルウォーターのような水が望ましいです。
Q
尿検査を受ける前に気をつけた方がいい事は何ですか?
A
- 多量のビタミンC摂取・・・尿中のブドウ糖、赤血球反応に影響します。
- 激しい運動後・・・尿蛋白が陽性に出る事があります。安静時に採尿してください。
- 生理中・・・採尿時に血液が混入する可能性が高いため、生理時の検査はなるべく避けてください。
Q
中間尿を採るように言われました。中間尿の採り方教えてください。
A
最初と最後の尿は入れずに中間の尿を採りましょう。細菌などの混入を防ぐ目的です。
便の検査に関するもの
Q
採便後の容器の保管方法教えてください
A
暑い場所や室温(20℃以上)などに保管した場合、正しい結果が出ないことがあります。
冷暗所で5日間ほど保管可能ですが、なるべく早く病院に提出してください。
輸血検査に関するQ&A
Q
献血した血液はどのようにして使われるの?
A
善意で献血していただいた血液は、日本赤十字社の血液センターで血液型検査や感染症予防のための厳しい検査を行い、陰性のものだけを使用しています。
Q
自己血輸血について教えて
A
輸血には同種血輸血と自己血輸血があります。同種血輸血とは献血により得られた血液を輸血することで副作用(発熱、蕁麻疹、肝炎等)が発症する可能性は0%とはいえません。一方、自己血輸血はこのような副作用を回避するために行われます。
自己血輸血は十分な管理の下で行われれば最も安全な輸血であり、当院でも積極的に導入されています。ただし、自己血輸血は条件が合う(貧血がない、必要量を貯める時間的余裕がある等)患者さんに適応されるので詳しくは主治医にお尋ねください。
自己血輸血とは一般には『貯血式自己血輸血』を指しますので、簡単に説明します。
手術前(外来あるいは入院後)に患者さん自身の血液を採血・保管し、手術時に使用する方法です。予定された手術で一定の条件に合えば採用可能ですが、緊急手術では対応できません。
Q
輸血後感染症検査ってなに?
A
輸血用血液製剤は供給前に血液センターで感染原因となるウイルス検査など様々な感染防止対策が講じられていますが、最新の検査法を用いても感染被害を完全になくすことはできません。従って、血液製剤を媒介とした感染症の有無を確認するために、輸血2~3ヶ月後に輸血後感染症検査を実施する必要があります。また適正に使用した血液製剤によって万が一感染症等に罹患した場合は『生物由来製品感染等被害救済制度』により医療費、医療手当て、障害年金等の給付を受けることができます。
当院輸血部門では、輸血をされた患者さんの元にうかがって個々に輸血後感染症検査についての説明を行っています。
Q
赤ちゃんの血液型を知りたいのですが・・・
A
ABO血液型は赤血球上の抗原を検査する『オモテ試験』と血清中の抗体を検査する『ウラ試験』を行い、両者が一致した場合に判定するのが原則です。乳幼児は抗体が充分産生されていないため、『ウラ試験』が正確に判定できず『オモテ試験』のみの判定となり厳密な意味で正確な血液型とはいえません。
輸血が必要な場合を除き学齢期程度まで待って血液型検査を実施するのがよいと考えられます。
なお、「血液型を知っておく」ためだけに行う検査は健康保険の対象外で自費となります。
細菌検査に関するQ&A
Q
血液に菌がいることがあるのですか?
A
通常はありません。身体が弱っているときなどに血液中に細菌侵入し、重篤な感染症を起こします。
Q
膀胱炎の原因となる細菌はなんですか?
A
大腸菌が最も多く、便に含まれる腸内細菌がほとんどです。
Q
食中毒にならないために何に気をつけたらよいでしょうか?
A
調理器具を清潔に保つこと、手洗いの励行、食品の十分な加熱などに気をつけてください。
Q
細菌検査の結果が遅いのはどうして?
A
1~2日菌を育ててから検査をするので時間がかかります。
Q
細菌の検査費用が2回に渡って請求されました、どうして?
A
培養検査は時間がかかるため、どんな菌が生えてきてどんな検査が必要か、数日たたないとわかりません。検査した菌数によって請求金額が変わってきますので、後日追加で会計請求をさせていただいています。
生理機能検査に関するQ&A
Q
心電図ってどんな検査?
A
心電図検査は、心臓病を見つけるための基本的な検査で、心臓の筋肉が収縮する時に発生する電気信号を記録します。その変化を波形のグラフに表すことで、心臓が規則正しいリズムで動いているかどうかを見る事ができます。
ベッドに仰向けに寝て胸に6ヶ所、両手首、両足首の合計10ヶ所に電極を貼り付け、5分間ほど心臓の電気信号をとらえ記録します。
運動の後や、寒さや緊張で体が震えている時は正確な検査ができないので、安静にしてリラックスした状態で行ないます。
Q
ホルター心電図ってどんな検査?
A
人は日常、活動しているときに心身の負荷を受けてさまざまな自覚症状を訴える場合が多く、また一方では、安静時や夜間に心臓に関連する発作を起こす場合も知られています。 このような状況の中で、24時間いつでもどこでも心電図を記録するのがホルター心電図なのです。 胸が痛いのに、心電図をとってもなんでもないと言われる・・・胸が痛かったのに病院に着いたら治ってしまう・・・こんな方にもホルター心電図がお勧めです。
Q
肺機能って何をみるの?
A
基本的な検査は二種類あります。VC(肺機能分画volume curve)、FV(強制呼出曲線flow volume)です。VCから一回換気量、予備吸気量、予備呼気量、それとFVからの流速・流量曲線から一秒率(最初の一秒間の呼出で全肺活量の何%を吐き出せるか?正常値70%以上)や曲線のカーブより、末梢気道病変、肺繊維症、肺気腫、喘息などを知ることができます。
Q
超音波(エコー)検査ってどんな検査?
A
人間が聞き取ることのできない音(超音波)を使って体内の病変を探し出す検査です。超音波は放射線と違い、被爆の心配はありません。
そのため妊娠中の女性や、胎児に対しても繰り返し検査することができます。
Q
エコー検査では何故食事を摂ってはいけないの?水や薬は飲んでいいの?
A
腹部エコーは基本的に絶食となります。食事を摂ることによって、胆嚢が小さくなって超音波で見え難くなってしまいます。そうすると胆嚢内部にポリープや結石があっても分かり難くなってしまいます。
また、胃の中に食物が入ることにより、胃の背中側にある膵臓が見え難くなります。ただし、お水・お茶のみ(ジュース・牛乳不可)飲んでいただいても結構です。内服薬については、普段服用されているものは飲んでください。(ただし、糖尿病で経口血糖降下剤やインスリンを服用の方は、担当医とご相談ください。)
血管エコーや乳腺エコー、心エコーには食事制限はありません。