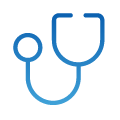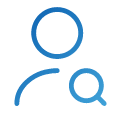化学療法室
/ 診療科・部門
化学療法室の紹介
外来に受診され点滴を受けられる患者さんは、当院2階にある化学療法室で点滴を行います。ここでは、化学療法(抗がん剤)、点滴や注射を実施しています。
近年がんの化学療法は、新しい治療メニューや抗がん剤の開発、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など次々に新しい薬剤が使用されるようになりました。また、それらを組み合わせての治療など、日々進化し、外来で治療することがますます増えています。短い方で30分、長い方は7時間ほど治療にかかることもあります。それでも、外来で化学療法を行うことは、ご家族との生活や仕事等で自分の役割を果たしながら治療を続けていくことができ、患者さんの生活の質(QOL)の向上につながります。


実際の化学療法の管理体制と流れ
薬剤科では医師の指示書(注射処方せん)に従って、治療前日に複数の薬剤師による確認の上で薬剤を準備します。
治療当日、主治医は患者さんを診察し、検査結果を確認した上で化学療法を実際施行するかどうかを決定します。実施決定後、薬剤科では抗がん剤プロトコールに従っているかを確認するため、再度検査値の確認を行います。治療延期や減量規定に該当する場合は医師への確認を行います。確認終了後、薬剤師は安全キャビネット内で無菌的に抗がん剤等の調製(ミキシング)を行い化学療法室に払い出します。
患者さんへ点滴する前に、化学療法室の看護師同士での確認後、患者さんと一緒に名前と生年月日、薬剤、時間などの確認を行います。1本ずつ交換のたびに携帯端末で確認を行い厳重にチェックしています。 その後、医師または看護師が静脈ラインを留置針にて穿刺し点滴の準備をします。薬剤によっては、医師が逆血を確認します。
点滴中は、看護師が患者さんの状態を確認し必要に応じてモニターを使用して安全管理を行っていきます。化学療法実施中や終了時に体調に変化がないか、また静脈ライン穿刺部位に異常がないかを確認し、安全確保に努めています。
緊急時の対応
外来化学療法施行時の緊急事態に迅速に対応できるように、各種マニュアルを用意しています。実際の化学療法で最も多いトラブルとして知られている薬剤の血管外漏出やアレルギーにも速やかに対応できるようにマニュアルやモニターを完備して、診療科と連携しながら対応しています。
抗がん剤の点滴を行う場合、医療スタッフが患者さんの安全の確保に十分配慮しながら実施しております。点滴漏れや過敏症の発現など副作用が生じた場合も慎重に対応を図っています。
また、自宅で副作用が生じた場合の緊急時対策等についても患者さんへ十分な情報を提供しており、在宅での治療が安全に継続できるよう取り組んでいます。
ベッド、リクライニングチェアが配備され、患者さんの状態やアレルギーのリスクなどを考えて選択しています。それ以外は自由に選ぶことができます。
治療中はリラックスした気分で治療を受けていただくために音楽をかけています。テレビ鑑賞ができるベッドも3ベッドあり、利用を希望する場合は声をかけてください。(テレビカード、イヤホンの準備をお願いします)
スタッフは専任医師、当番医師、がん薬物療法認定薬剤師、看護師で構成され、治療や副作用への対応をしています。生活面での不安や支障にも目を向けていますので、遠慮なくスタッフに声をかけてください。痛み、不安などについてはがんよろず相談でも相談を受けています。
また、栄養士による栄養指導なども行っています。
有害事象に対する予防や対策について
看護師は、化学療法当日の患者さんの治療の流れや帰宅後の注意事項や副作用が生じた場合の連絡等について、具体的な説明を行います。
また、業者と協力して脱毛時の頭皮ケアやウイッグ購入における補助金について、ウイッグの試着などの説明も行います。また、治療に使用する薬剤について薬剤師から説明を行っています。
当院の化学療法運用システムについて
当院のがん化学療法運用システムについて紹介します。
1.抗がん剤プロトコール管理
当院ではがん化学療法が適正かつ安全に行われるために、がん化学療法小委員会で抗がん剤プロトコール(レジメン)の審議および管理を行っています。
抗がん剤プロトコールとは、あらかじめ定められた治療計画書であり、使用薬剤、投与量、投与方法などについて規定しています。抗がん剤プロトコールは登録制とし、がん化学療法小委員会で審議し承認されたプロトコールのみを使用しております。
当院ではがん化学療法が適正かつ安全に行われるために、がん化学療法小委員会で抗がん剤プロトコール(レジメン)の審議および管理を行っています。
抗がん剤プロトコールとは、あらかじめ定められた治療計画書であり、使用薬剤、投与量、投与方法などについて規定しています。抗がん剤プロトコールは登録制とし、がん化学療法小委員会で審議し承認されたプロトコールのみを使用しております。
2.がん化学療法についての説明について
医師は患者さんに現在の病名と病状、治療の選択についてわかりやすく説明し、患者さん本人が十分納得した上で治療を開始するようにしています。
説明に用いる文書は各診療科で統一したものを用い、薬の説明から副作用の発現頻度まで詳細な説明を行います。
薬剤師は、医師の治療方針と患者情報を事前に確認した上で、抗がん剤プロトコールに従って薬の適正使用の確認を行います。
また、患者さんへ医師の説明を補足するため以下の点について説明を行います。
- 抗がん剤プロトコール名称
- 薬剤名と薬効について
- 投与スケジュール、投与経路、投与時間、注意点について
- 予想される有害事象(副作用)と自覚症状について
- 有害事象に対する予防や対策について
外来点滴治療センターの近年の外来化学療法延べ患者数
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 1,076 | 1,142 | 1,215 | 1,062 | 803 |
| 消化器内科 | 513 | 597 | 766 | 705 | 762 |
| 血液内科 | 139 | 200 | 232 | 381 | 412 |
| 泌尿器科 | 250 | 278 | 262 | 390 | 489 |
| 耳鼻咽喉科 | 65 | 40 | 46 | 108 | 101 |
| 総合診療内科 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 脳神経外科 | 9 | 31 | 11 | 19 | 35 |
| 整形外科 | 26 | 7 | 13 | 16 | 19 |
| 腎臓内科 | 25 | 40 | 32 | 41 | 46 |
| 婦人科 | 42 | 158 | 412 | 584 | 458 |
| 脳神経内科 | 5 | 10 | 56 | 104 | 184 |
| 合計 | 2,161 | 2,503 | 3,048 | 3,412 | 3,312 |