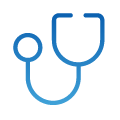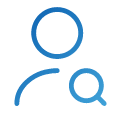血液内科
/ 診療科・部門
概要
診療紹介
血液に関係する全般の疾患を取り扱っています。入院診療では主にがん化学療法を行っています。新たな分子標的薬が登場してきており治療方針を再検討し治療の制度を高められるよう努めています。
2019年3月まで血液内科常勤医が不在であったこと、および現在のところ常勤医が一人であることから、外来は院内からの紹介及び他施設血液内科からの紹介のみを受け入れています。
まずはかかりつけ医より、当院総合診療内科に紹介状と共に予約を取っていただいています。血液内科受診の必要があるようでしたら、血液内科へ紹介となります。
他施設血液内科からの紹介の場合は、地域医療連携室へ連絡をいただいた後、外来・入院の予約を取ります。
造血器疾患の中には早急な処置を要する疾患もあります。その際は例外として対応しますので、電話連絡をお願いします(外来日は火曜日・金曜日ですが、担当医がいる限り曜日に関係なく対応します)。
血液内科の診察では血液検査データが欠かせません。このため来院後直ちに採血を行うことをお願いしています。血液検査の結果が出た後に診察となります。検査結果が出るまでに1~1.5時間程度を要するため、診察予約時間の1~1.5時間前来院され、採血するようお願いします。
主な対象疾患
- 造血器悪性腫瘍
(急性および慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等) - 骨髄不全症候群
(骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、発作性夜間血色素尿症等) - 造血器関連自己免疫疾患
(特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血等) - その他
血友病・HIV 感染症には対応できません。
その他
造血器疾患は研究材料が比較的採取しやすいことから、治療分野、とりわけ悪性腫瘍治療ついては進歩が最も著しい領域と言えます。造血器悪性腫瘍の治療の中心となるのは、複数の抗がん剤を用いる多剤併用がん化学療法です。これに必要に応じて骨髄移植を代表とする造血幹細胞移植が併用されます。
有効な抗がん剤の種類は驚くほど増え、これまでの一般的な抗がん剤に加え、分子生物学的な機序で効果を示す薬剤が多数用いられるようになりました ( 一部の急性骨髄性白血病で使用されるベサノイドやマイロターグ、慢性骨髄性白血病で使用されるグリベック、悪性リンパ腫で使用されるリツキサンなど )。この他にもこれまでの抗がん剤とは作用機序がまったく異なるプロテアゾーム阻害剤、砒素やサリドマイドなどもごく普通に使用されるようなっています。造血幹細胞移植もその目的を大きく変えています。以前は大量の抗がん剤投与や放射線照射を行うことを目的として行われていましたが、現在では同種免疫効果により抗がん剤抵抗性の腫瘍細胞を殺すことが主眼となっています。このため「ミニ移植」と言った少量の抗がん剤や放射線照射だけで行う移植法が確立しました。またこれまでは「HLA」と言う体中の細胞についている名札が一致している人から造血幹細胞を提供していただく必要がありましたが、現在ではある程度一致していなくても移植が可能になってきました ( ミスマッチ移植 )。そしてミニ移植とミスマッチ移植により移植が可能となる患者さんの数は飛躍的に増えています。
治療法が進歩し、治療選択肢が増える事は大変喜ばしいことです。しかし、大きな問題も生じてきます。それは「どの治療法が今の自分に最もふさわしいのか」という問題です。
この問題を解決するためには、まず自分の疾患について充分に理解することが不可欠です。しかし血液疾患は肺癌や胃癌などの固形癌とは異なり、多くの場合「塊り」を作らないため、患者さんは疾患イメージをつかみにくく、自分自身の病気を充分に理解していないことが少なくありません。また治療法の選択には、疾患の進行度・合併症の有無・全身状態・社会的状態なども大きく影響を与え、同じ疾患の患者間であっても、「今自分にとって最もよい治療」は変わることでしょう。ですから病名・病状を患者さんにわかる言葉でお話しする「告知」なくしては、当然のことながらその先の治療法の選択には進むことはできません。
次にようやく各治療法の説明となります。各治療の有利な点と不利な点について理解していただくことになります。そしてどの方法が自分自身にとって最もふさわしいのか判断していただきます。
しかし実際のところは、どんなに説明を重ねても、本来の意味での充分なインフォームド・コンセントは不可能なのが実情です。その理由はいくつかあります。まず重篤な疾患名を告げられて動揺してしまっていることです。次に、普段耳にすることが少ない科学やリスクマネージメント等の内容に、頭の処理が追いつかないことです。そしてインフォームド・コンセントって言葉は知ってはいても、患者自身の責任で治療法を選択するなどとは考えたこともないことです。更に改めてじっくり考えるにのに充分な時間を、疾患が与えてくれないことも少なくありません。これまで、「どこが解らないか解らない」という言葉を何度も耳にしてきました。このため当科としては、「自分や自分の家族が目の前の患者さんと同じ病気になった時に、どのように対応するか、対応して欲しいか」という点を第一に考えて臨みます。
医師紹介
-
望月 康弘 / もちづき やすひろ
-
役職
- 血液内科長
-
専門分野
- 血液内科
-
資格
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- 日本血液学会認定血液専門医・指導医
- 日本造血細胞移植学会認定医
- 日本輸血細胞治療学会認定医
- 日本がん治療専門医機構認定医
- 日本感染症学会認定感染症専門医・指導医
- 医学博士(甲)
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
-
外来担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 |
望月 康弘 |
望月 康弘 |
望月 康弘 (初診・要予約) |
海老澤 和俊 (非常勤) |
牧 宏彰 9・16・23・30 |
| 午 後 |
ー |
望月 康弘 |
ー | 海老澤 和俊 (非常勤) |
牧 宏彰 9・16・23・30 |
- 受診には他施設の血液内科医師よりの紹介状・予約が必要です
休診情報
休診・代診はありません。