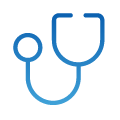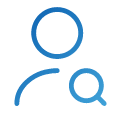急に脳の血管がつまることを言います。突然に半身が麻痺したり、言葉がおかしくなったりします。イーと言った時に顔がゆがんだり、両手を挙げたときに片方の手が落ちたり、ろれつが回らなかったり、言葉が出てこなくなったりします。救急車を 要請してください。時間の経過により血管の壁が変化し、細くなりあるとき血管が詰まるのは想像できると思います。通常は高血圧や糖尿病、喫煙など、動脈硬化を起こしやすい素因をもった方に生じます。
動脈硬化の危険因子を持っていなくても心臓の不整脈が原因で起きることがあります。発作性心房細動と言い、自分では気づかずに、数分や数時間の間、脈が不規則になります。日本循環器学会の疫学調査では,有病率は70歳代で男性3.4%,女性1.1%,80歳以上では男性4.4%,女性2.2%です。この不整脈が起きている間に、心臓の中にゆっくりと血栓ができて、それが脳の血管に流れて瞬時につまることがあります。これを心原性脳塞栓症と言います。日本脳卒中協会は3月9日を脈の日として、検脈をよびかけています。
脳梗塞の治療はすみやかに積極的に行うことが原則です。発症して4.5時間以内に治療が行える場合は、造影剤(血管に色がつく)を使用してCTを撮影し、どの血管が閉塞しているかを確認します。禁忌事項がないかを確認した後、血栓を溶かす薬剤を投与します。大きな血管が閉塞している場合は脳外科に依頼し、カテーテルという軟らかい針金のようなものを足の付け根から挿入して血栓をとりのぞく血栓回収療法を行います。それらを行わないほうがよいと判断した場合も血小板や凝固因子(のりのような働きをするもの)の働きを弱めて血液の流れをなるべく維持する抗血栓療法を積極的に行います。また脳保護薬を併用することが多いです。積極的にリハビリテーションも行います。
脳神経内科
/ 診療科・部門
概要
診療紹介
脳神経内科は脳から脊髄、末梢神経を介して筋肉、皮膚に至るまでの経路の障害を診療しています。とても広い範囲の問題の解決を日常行っています。
患者さんの訴えとしては、力が入りにくく重い、疲れやすいなどの筋力低下、以前と比較してうまく歩けない、歩き方がおかしいなどの歩行障害、手足のしびれ、感覚が鈍い、めまい、頭痛、ものが二重に見える、呂律が回らない、痙攣発作、普段と比べて受け答えや様子がおかしいなどの意識障害といった種々のものがあります。
検査としては、CT、MRI、脳波がよく行われます。他に筋電図検査、髄液検査などが必要なこともあります。
脳神経外科はもちろん他の内科や整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、精神科などとの関連も深く相談しながら協力して診療にあたっています。
どんな問題も神経系につながっているので受診先の医師(かかりつけ医)から脳神経内科へ受診するようにとの話があれば受診を検討していただきたいと思います。
脳神経内科に初めて受診される方へ
脳神経内科に初めて受診される患者さん(受診歴があっても初診扱いになる人も含みます)につきましては、「かかりつけ医の紹介状を必要とする完全予約制」になっています。予約のない患者さんは地域医療連携室にて予約をおとりください。
主な対象疾患
脳梗塞
脳出血
脳出血は脳の中で細い血管がはぜることを言います。脳の表面の太い血管が破れることをくも膜下出血といって区別しています。症状は軽いものから重いものまであり、症状は脳梗塞と区別がつかないことが多いです。高血圧や喫煙、過度のアルコール摂取が原因になります。治療は血圧を頻回に測定して、薬剤で血圧を下げることと止血剤を投与します。大きい脳出血は出血部位によっては、脳外科で血腫除去術を行います。
てんかん
昔は子どもの病気でした。最近は圧倒的に高齢の方に多くなっています。軽くない脳卒中になったり外傷を負われたり、認知症などが原因で起きることも多いです。朝にからだが一瞬ピクッとする若い方に多いてんかんもございます。てんかんは、毎回決まって同じように始まって、同じように回復するような“発作”というものを繰返す疾患です。全身または半身の手足がピーンとのびたあと、ガクガクするものを痙攣発作といいます。口をもぐもぐしたり、一点を見つめたり左右どちらかに眼が寄ったり、身体の動作が止ったりして数十秒で回復するものも痙攣はないですが発作です。本人に確認すると、胸部や腹部の不快感を感じたり、既視感を感じたり前兆があることがあります。
現在は抗痙攣薬の選択肢も増えて、副作用が少ない薬剤で治療を行うことが可能となっています。
パーキンソン病
動作がゆっくりになることが特徴です。髪を洗ったりお米をといだりハンドルを切る際にどちらかの手が思うように素早く動かないことや、歩く様子がゆっくりでどちらかの足が前に出にくいことなどに、始めに気づくことがあります。静かにしていると手や足がゆっくり振るえる振戦という症状は7割程度の方に見られます。便秘や立ちくらみなどの自律神経の症状や
睡眠中の寝言、頑固な痛みや不安、気分が落ち込みやすいことも見られることがあり、すべてパーキンソン病による症状と考えられています。
治療はお薬でドパミンを補充しながら元気に生活するのが大切です。他にもいろいろな治療の選択肢(脳深部刺激療法,レボドパカルビドパ経腸療法,持続皮下注療法など)があり、適宜相談していきます。よくお話をして楽しく生活すること。よく運動すること。よく睡眠をとること。さらに大切なのは、よく食べて、お腹の調子を整える薬剤の力を借りてもよいので、排便管理を積極的に行うことが大切です。
パーキンソン症候群
最初はパーキンソン病と診断して治療を行っていて、その後症状が進行することで初めてパーキンソン病ではなく、パーキンソン症候群が原因であることがわかることも稀ではありません。代表的な疾患に、多系統萎縮症と進行性核上性麻痺があります。
小さな脳梗塞が時間をかけて複数生じていたり(脳血管性パーキンソン症候群)、服薬している薬剤がドパミンを遮断する作用がある場合に(薬剤性パーキンソン症候群)症状が生じることがあります。
筋萎縮性側索硬化症
ALSという言葉のほうが聞いたことがあるかもしれません。脳や脊髄にある運動神経の細胞が徐々に減っていくことで筋肉が萎縮して力が入りにくくなる疾患です。遺伝性の原因が1割程度にみられ、その一部の遺伝子の変異に対してRNAに対する治療が試みられています。治療法は日進月歩で、2023年にエダラボンの内服が使用できるようになり、2024年にメコバラミンが使用できるようになりました。筋力低下が進行していく中で積極的に過ごせるように対症療法や生活の工夫をすることが大切であるため一緒に進めてまいります。最先端の研究では脳内に埋め込まれたセンサーが脳信号を読み取って音声に変換する装置がうまく作動したことを報告しています。
脊髄小脳変性症
小脳は身体の動きを調節する働きをしています。脳のいろいろな場所と情報のやりとりをして、身体の動きを調節します。小脳がうまく働かなくなると、階段を降りるときや、でこぼこの道を歩くときにバランスがとりにくいなどの症状があります。原因が遺伝性である方が3割と比較的多く、遺伝性疾患に対しては新しい治療が期待されています。
遺伝性でない7割の方は原因がわからないことも多いですが、積極的に原因を調べて治療の可能性を検討しています。他の疾患でも同じですが、リハビリテーションを行いながら楽しんで生活をし、その都度過ごし方を検討していくことが大切だと考えています。
髄膜炎
症状は発熱と頭痛、吐き気や羞明などです。風邪の延長(エンテロウイルス)であることがおおく大半は自然に改善します。
海外の報告では単純ヘルペス2型が17%、帯状疱疹ウイルスが8%を占め、これらのウイルスはアシクロビルという抗ウイルス薬の点滴が効果があるので、当院ではほとんどの方に投薬しています。
細菌性髄膜炎は一刻も争う感染症で、上記の頭痛、発熱、嘔吐に加えてほとんどの方に意識障害(様子がおかしい)を伴っています。ウイルスではなく細菌が相手です。すぐに抗生剤とステロイド治療を開始してから検査を行います。
他にも結核性髄膜炎、真菌性髄膜炎、癌性髄膜炎などがあります。
脳炎
細菌性髄膜炎と一緒で一刻を争います。単純ヘルペス1型をはじめとして、いろいろなウイルスが原因になります。ウイルス性髄膜炎と同様にアシクロビルという抗ウイルス剤を点滴します。他に自己免疫介在性脳炎と言って、自分の免疫が自分の脳の一部を誤って認識し、結果として悪い病原体はいないのに炎症を起こしてしまう疾患があります。ステロイドや免疫抑制剤などを使用して治療を行います。
多発性硬化症(MS)
多発性硬化症は世界的にも日本でも緯度の高い地域ほど頻度が高いとされています。日本では10万人あたり10人程度ですが、欧米では10万人あたり50~200人程度と多いです。比較的若い方に多い疾患です。脳や視神経や脊髄などの神経の一部の小さな範囲に炎症が生じて、しびれをはじめとする様々な症状が現れるようになる病気です。MSになると多くの場合、症状が出る「再発」と、症状が治まる「寛解」を繰り返します。主に再発時のステロイドを中心とした急性期治療と再発や進行を予防する治療に分かれます。最近はさまざまな効果のすぐれた治療薬があり、積極的に再発や進行を予防することができるようになりました。
視神経脊髄炎(NMOSD,MOGAD)
NMOSDは10万人あたり1~3人程度の頻度です。多発性硬化症に比べて年齢が高く圧倒的に女性に多いという特徴があります。AQP4抗体が原因となっていることがわかっています。吃逆や嘔気を経験することが多く、視神経炎では目が見えにくい、視野が欠ける、眼の奥が痛いなどの症状が表れます。脊髄炎では手足や胸部、背部がしびれる、その一部が痛む、徐々に手足の力が入りにくくなったり排尿が困難になったりするなどの症状があります。急性期の治療はステロイド治療と血液浄化療法を速やかに行います。症状が落ち着いたら再発予防を行います。ステロイドや免疫抑制剤の他に、2019年以降に優れた効果を持つ予防薬が使用できるようになっています。
MOG抗体が原因となっている疾患(MOGAD)もわかりました。急性期の治療は一緒で、再発予防はステロイドや免疫抑制剤が使用されています。最近MOGADも再発予防治療の臨床試験が行われており、より有効性の高い薬剤が使用できるようになることが予測されます。
重症筋無力症(MG)
非常に頻度の多い疾患です。昔は治療法がなかったので重症となっていますが、今の若い医師で重症だと思っている先生はいないと思います。筋肉が疲れやすいという特徴があり、周囲からは症状がわかりにくいと言われます。脳からの指令が末梢神経という神経の最も末端に届くとそこから筋肉へ向かってアセチルコリンという伝達物質が放出されます。それを筋肉にある受け皿が受け取ると筋肉がギュッと収縮します。この疾患では筋肉の受け皿に対して、誤って自分の免疫が抗体を産生して攻撃してしまうことで伝達物質に反応できる受け皿が減ってしまいます。少ない受け皿で次々と長い時間指令を受け取っていると、多い受け皿で対応しているときと比べて段々対応できなくなります。これが疲れやすさのメカニズムです。
治療は受け皿の炎症を抑えることです。ステロイドを中心とした免疫抑制剤を使用します。また原因の抗体を除去する血液浄化療法や原因の抗体をはやく壊してしまう免疫グロブリン大量静注療法があります。ある程度落ち着いたら少量のステロイド(5mg以下)と免疫抑制剤を中心に受け皿に対する炎症を抑えて、症状がほとんどなく生活できることを目標に治療を行います。2018年から2024年にかけて4種類の新しい治療選択肢が増え、疲れやすくて生活に制限があった方にも積極的に治療を行っています。
筋炎
大きく分けて皮膚筋炎、多発筋炎、壊死性筋炎、封入体筋炎があります。
封入体筋炎はやや特殊な疾患で炎症の要素と筋肉が勝手に壊れていく(変性)の要素があります。
皮膚筋炎や多発筋炎は膠原病にも分類されます。自分の免疫が誤って筋肉を攻撃してしまう疾患です。腫瘍が背景にあって、それに対する免疫が筋肉も攻撃してしまうことがあります。そのため筋炎の診断時には悪性疾患が隠れていないか精査を状態に合わせて行っていきます。
これらの筋炎の特徴は、最近いろいろな自己抗体がわかってきたことから、その自己抗体を検査することによりこれらの筋炎の特徴を前もって把握することが可能となりました。
治療はステロイドや免疫抑制剤が中心となります。
ギラン・バレー症候群(AIDP,AMAN)
末梢神経に急激に炎症が生じる疾患です。末梢神経は脳から脊髄を通って手や足に神経が配線のように張り巡らされています。炎症を起こす原因は自分の免疫にあります。
何らかのウイルスや細菌に感染した後で、それに対する免疫が偶然自分の神経線維を攻撃するようになってしまいます。
末梢神経には運動神経(脳から手足を動かす指令が伝わる)、感覚神経(手足で感じた情報を無意識に脳に送る)、自律神経(体温や血圧、脈拍、腸や膀胱の調節を無意識に自動的に行う)が含まれています。運動神経だけが影響を受ける軸索型と運動や感覚、自律神経が含まれる脱髄型に大きく分けられます。治療は炎症を起こす抗体を薄めたり早めに壊れたりするように大量免疫グロブリン静注療法やその抗体を機械で除去してしまう血漿交換療法があります。3週間以内にピークに達した後は徐々に神経が修復されていき、回復に向かっていきます。重症で回復が困難な方もまれにおり、より有効な治療を行うために国内でもさかんに臨床試験が行われています。
コロナウイルスに対する対策から皆が外出を控えてマスクをして生活した数年は、当院では全く診療することがありませんでした。2023年から徐々に発生が増加しています。活発に活動すると感染する機会も増えて、その結果ギラン・バレー症候群も増えているものと理解しています。
慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)
発症時はギラン・バレーと区別がつきにくいことがあります。やはり末梢神経が炎症で損傷されて手足に力が入りにくくなる疾患です。ギラン・バレーは症状が日に日に進行しますがCIDPはゆっくりと進みます。当院へお越しになるまでに数週間くらい経過していることが普通です。原因はわかりませんが、自分の末梢神経に対する抗体(異物が侵入してきたときにリンパ球が相手を捕まえる武器)が神経を傷付けているだろうと考えられています。その抗体を中和したり早く壊したりするための大量免疫グロブリン静注療法や、その抗体を機械的に除去するための血漿交換療法を行います。またその抗体を作らせないようにステロイドなどの免疫抑制剤(免疫を抑えて、リンパ球が武器をつくるのを邪魔する)を使用して治療します。7割くらいの方は劇的に効果があるのが特徴です。
CIDPは大きく3つに分かれると考えられています。
まず、腕と手、太ももと足の筋肉が均等に障害を受けるのが典型的CIDPです。大量免疫グロブリン静注療法は劇的に効果があります。他に血漿交換療法、免疫抑制療法も効果的です。
次に、年単位でゆっくり進む場合です。小指に力が入りにくかったり足首に力が入りにくかったりして入りにくい場所に偏りがあり、左右でも差があります。多巣性脱髄性感覚運動型と言います。治療の基本はステロイドなどの免疫抑制剤と大量免疫グロブリン静注となります。
最後に手足の先だけ力が入りにくくしびれるタイプがあります。遠位型といいます。このタイプでは原因となる抗体がはっきりとわかってきたのが特徴です。いったん症状がよくなったら、それが悪化しないように維持治療を行います。ステロイドなどの少量の免疫抑制剤やグロブリン静注療法の他にグロブリン皮下注療法(自宅で行える)もあります。維持するためにさらに新しい薬剤が選択枝に加わる予定です。
多発神経炎
足先からゆっくりと膝の方までしびれが広がったり、さらに手にもしびれを感じたりするようになります。ゆっくりと何ヶ月もかかって進みます。原因は糖尿病やアルコール、抗がん剤などの薬剤などが代表的ですが、神経内科医師にとってもっとも診断がむずかしいタイプの末梢神経障害です。左右対称で両足の先からしびれが段々広がるのが特徴です。
いずれにせよ、神経内科医師にとって腕の見せ所であります。
血管炎症候群
顕微鏡で見るような非常に細い血管が炎症を起こして、その細い血管の血流が滞るようになります。細い血管が障害を受けてもっとも困るのは末梢神経です。末梢神経に蔦のように絡んでいる細い血管の流れが悪くなると途端にその末梢神経はダメージを受けます。そのようにして手足のいろいろな部分が急にしびれて動かなくなります。痛みもあったりそこがむくんだりもします。血管の炎症ですからそれを改善するためには炎症を抑えるようにステロイドなどの免疫抑制剤を使用します。
遺伝性ニューロパチー
シャルコーマリートゥース病、アミロイドーシスなどいろいろ原因があります。
特徴をしっかりと捉えて、診断に結びつけています。遺伝子異常がわかっているものが多いので、今後治療ができるようになっていくと期待されています。
筋疾患
筋強直性ジストロフィーをはじめとして、遺伝性の筋疾患が多数ございます。
筋強直性ジストロフィーは筋肉の疾患の中では罹患されている方が最も多い病気です。
日本の研究者が見出した薬剤が有望な薬として臨床試験が行われています。心電図や肺活量、血液検査などを定期的に行っていきます。
脳神経内科のもう少し具体的な紹介
脳神経内科長 鈴木洋司
医師のカルテでは、患者さんの主訴である受診していただいた理由を大切にしています。
急病に分類される脳神経内科の主訴はいずれも数秒や数日で急におかしくなったものを指します。急病は救急車を呼ぶことをためらわず、あるいは救急外来を受診してください。
急病ではない場合については、段々症状が気になるようになった場合です。
数週間で進んでいるのか、数ヶ月から数年の単位で経過しているのか、あるいは良くなったり悪くなったりしているのかによって想定する疾患が全く変わってきます。
仕事や家事が上手くできなくなった、何度も約束を忘れてしまう、スマートホンがうまく使用できない、話したい言葉が出てこない、車の運転がうまくできないなどの高次脳機能の症状があります。
その他には徐々に階段を降りるのが怖くなったり、階段を登る際に手すりが必要になったり、家の中や外を歩きにくくなったり、歩き方がおかしくなったり、ゆっくりになったりする歩行障害があります。しびれの範囲が広がったり、字を書いたりお箸を使うことが下手になったり、呂律が回りにくくなったり、飲み込むのが大変になったり、手足の震えなども脳神経内科で専門的に診療する疾患が多く含まれます。
これらの症状があり診療所の先生(かかりつけ医)に相談していただくと、当科を紹介されることがあると思います。
最後に検査についても簡単に説明します。
当科も血液検査とCTやMRIなどの断層写真を行います。これらは原因を調べる上で簡便で有効な方法です。
また、下記の検査を実施することがあります。
脳波は脳の心電図と言える、脳で生じる症状を分析する大切な検査です。1時間程度かかる検査で患者さんには静かな部屋で横になっていただきます。検査中はうとうとしていただいた方が良い情報が得られます。
髄液検査も行うことがあります。脳髄液は脳や脊髄などの神経の集まった束と頭蓋骨や脊椎などの神経の入れ物の間にあります。穿刺しても安全な場所に細い針を使ってその液体を採取します。有用な情報が得られることが稀ではありません。
脳や脊髄の先には末梢神経(手足に配られる糸のような配線)や筋肉があります。末梢神経伝導検査は、皮膚の上からその末梢神経を強くない電気で刺激し、その伝わり方に異常がないかを調べる検査です。
筋電図は筋肉の活動を直接把握する検査です。筋肉がやせてしまう(末梢神経や筋肉の病気)原因を詳しく調べるために行うことがあります。
医師紹介
-
酒井 直樹 / さかい なおき
-
役職
- 副病院長 兼 医療の質管理センター長 兼 患者支援センター 認知症ケア支援室長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- 日本神経学会認定神経内科専門医・指導医
- 日本内科学会認定医
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- 日本認知症学会認定認知症専門医・指導医
- 臨床研修指導医
- ボトックス講習・実技セミナー修了
- TPA講習修了
- 国立大学法人浜松医科大学臨床教授
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
-
-
鈴木 洋司 / すずき ようじ
-
役職
- 脳神経内科長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- 日本神経学会認定神経内科専門医・指導医
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- 神経免疫診療認定医
- 臨床研修指導医
- ボトックス講習・実技セミナー修了
- TPA講習修了
-
-
森下 直樹 / もりした なおき
-
役職
- 脳神経疾患センター長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- 日本神経学会認定神経内科専門医
- 日本内科学会認定内科医・指導医
- 日本認知症学会専門医・指導医
- 神経免疫診療認定医
- 臨床研修指導医
- ITB療法WEB講習修了
- ボトックス講習・実技セミナー修了
- TPA講習修了
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
- 日本臨床神経生理学会専門医 筋電図・神経伝導分野
-
-
伊賀崎 翔太 / いがさき しょうた
-
役職
- 医長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- 日本内科学会認定内科医
- 日本神経学会認定神経内科専門医
- 日本脳卒中学会認定脳卒中専門医
- 日本脳神経血管内治療学会認定脳血管内治療専門医
- 日本脳神経超音波学会認定脳神経超音波検査士
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了
-
-
中村 圭吾 / なかむら けいご
-
役職
- 医長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- TPA講習修了
-
-
小関 昭仁 / こせき あきひと
-
役職
- 医長
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
資格
- 日本神経学会認定神経内科専門医
- 内科専門医
- 病院総合診療医
- ボトックス講習・実技セミナー修了
- TPA講習修了
- 総合診療専門研修特任指導医
-
-
岡 耕太 / おか こうた
-
役職
- 医員
-
専門分野
- 脳神経内科全般
-
外来担当医表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 |
1 | 鈴木 洋司 |
酒井 直樹 |
鈴木 洋司 |
岡 耕太 |
酒井 直樹 |
| 森下 直樹 |
中村 圭吾 |
森下 直樹 |
認知症外来 |
芹澤 正博(非常勤)13・27 |
||
|
伊賀崎翔太 |
小西 高志 (非常勤) 17 |
ー |
専門外来 5・19 |
ー | ||
| ー | ー |
小関 昭仁 |
ー | アルツハイマー外来 | ||
| 午 後 |
1 | 鈴木 洋司 |
酒井 直樹 |
鈴木 洋司 |
岡 耕太 |
酒井 直樹 |
|
伊賀崎翔太 |
中村 圭吾 |
小関 昭仁 |
鈴木 均 (非常勤) 12・26 |
ー | ||
| 森下 直樹 | ー | 森下 直樹 | ー | アルツハイマー外来 | ||
- 受診には紹介状・予約が必要です
- 認知症外来は他院から直接の紹介状・予約が必要です。
休診情報
休診・代診はありません。
診療実績
検査実績
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 神経伝導検査 | 230 | 220 | 330 | 273 |
| 筋電図 | 57 | 71 | 119 | 97 |
| 筋生検 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 神経生検 | 3 | 4 | 3 | 3 |
疾患別入院患者数
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 血管障害 | 208 | 199 | 201 |
209 |
| 感染症 | 16 | 5 | 16 | 21 |
| 脳・脊髄腫瘍 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 脊椎・脊髄疾患 | 21 | 17 | 18 | 15 |
| 水頭症・低髄液圧症候群 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 変性疾患 | 105 | 103 | 89 | 136 |
| 多発性硬化症・視神経脊髄炎 | 25 | 27 | 27 | 32 |
| 原因不明の脊髄炎・脳症・脳炎 | 20 | 35 | 37 | 17 |
| 筋疾患 | 9 | 23 | 33 | 40 |
| 末梢神経障害 | 39 | 31 | 37 | 62 |
| 不随意運動 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| てんかん けいれん | 55 | 49 | 69 | 56 |
| 意識消失発作 失神 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 一過性全健忘 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| めまい | 15 | 12 | 23 | 11 |
| 頭痛 しびれ | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 内科疾患に伴う神経障害 | 38 | 29 | 27 | 45 |
| 中毒 | 5 | 12 | 15 | 12 |
| 機能性神経障害 | 0 | 10 | 15 | 13 |
| その他 | 386 | 328 | 371 | 411 |
| 合計 | 959 | 892 | 1,001 | 1,098 |