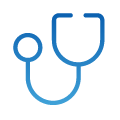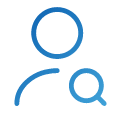リハビリテーション技術科
/ 診療科・部門
部門紹介
当院では理学療法・作業療法・言語聴覚療法・小児リハビリテーションで、医師の指示の下、個々の障害・症状にあわせて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリテーションを患者さんに提供させていただきます。
リハビリテーションの治療方針や目標などは、カンファレンス(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー)を定期的に開き、多職種にて連携をはかっています。
業務内容
理学療法(PT)
理学療法(Physical Therapy)は、病気や外傷や加齢などにより基本動作能力(座る・立つ、歩くなど)の回復・維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動や物理的手段を用いて機能回復・改善を図り、社会復帰や自立した日常生活を送れるように治療・指導を行います。
運動を治療手段に用いる運動療法には、関節可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、呼吸機能の回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療法と起き上がりから座位・歩行などの移動動作練習などが含まれます。
物理的手段を用いる物理療法には牽引療法、水治療法、電気療法、温熱療法などが含まれ、疼痛の緩和や軟部組織の緊張を緩和する目的に、運動療法と併行して行われています。
当院では、各科医師の指示のもと理学療法士が小児から高齢者まで、幅広く様々な方に理学療法を行っています。
作業療法(OT)
作業療法(OT)は、occupational therapy(作業療法)、occupational therapist(作業療法士)の略です。社団法人日本作業療法士協会(2018年)では「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す」としています。
作業は、私達が普段の日常生活に関わるすべての諸活動です。例えば、食事・更衣・入浴・トイレなど日常的な生活行為から、家事・趣味的な活動・仕事など多岐にわたります。病気や事故などによって身体や精神に障害を持った人に対して、その人が再び、家庭生活・社会生活をスムーズに送れるよう作業療法士が援助します。
言語聴覚療法(ST)
言語聴覚療法は、コミュニケーションの障害や食べることの障害へのリハビリを行います。
言語聴覚士(ST:SpeechーLanguage-Hearing Therapist)が、医師の指示の下、外来や入院にて赤ちゃんからご高齢の方まで対応しております。
地域の皆さんが豊かにコミュニケーションできるよう、また、おいしく食事がとれるよう貢献します。
小児リハビリテーション
小児科医師の指示のもと小児担当理学療法士(小児PT)、小児担当作業療法士(小児OT)、言語聴覚士(ST)でリハビリテーションを行っております。お子さん一人一人に合わせた目標を保護者さんと一緒に考え、日常生活の中でできることが増えるようにサポートいたします。
各療法について
理学療法
下肢の運動器疾患の理学療法
対象疾患
脊椎圧迫骨折・大腿骨頸部骨折術後・変形性(股・膝)関節症の人工関節置換術後・スポーツ等の外傷で膝の靱帯や半月板損傷・アキレス腱断裂・その他骨折をされた方。
手術の技術進歩により、受傷・術後翌日から運動療法が可能になっていますが、整形外科領域でも複数の疾患を持つ高齢者を対象とすることも多いため注意して治療を進めています。治療の進め方については、定期的に主治医と相談しています。
関節運動の拡大や筋力回復などの機能に対する訓練と、基本動作である起居動作・日常生活動作に対して訓練をしています。
また、早期の機能回復を目指して病室での自主トレーニングを指導しています。
当院では、変形性(股・膝)関節症の人工関節置換術の手術に力をいれています。術後は3週間程度を目安に自宅退院または転院されています。自宅退院後は理学療法を外来に移行して実施しています。
脳血管疾患・神経疾患に対する理学療法
脳血管疾患
脳梗塞・脳出血・脳挫傷・くも膜下出血、硬膜下出血、頭部挫傷等
神経疾患対象疾患
パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症・多発性硬化症等
早期からリハビリを開始することで体力や筋力低下の予防ができ、寝たきりや認知面の予防につながります。また、障害された機能の回復を図るとともに、残存機能を有効につかい、日常生活への影響をできる限り少なくするように促します。
内部障害等の廃用症候群の理学療法
病気等の治療に伴い長期間安静状態となり、運動量が減少したことで心身の様々な機能が低下する状態に対して離床を促し、活動性を拡大し体力や精神機能・認知面の改善を行います。
がんのリハビリテーション
がんの治療(手術後・放射線・化学療法)によって日常生活動作や体力の低下が生じた方を対象に患者さんやご家族の意向に添えるように介入して在宅復帰を目指します。
呼吸器疾患の呼吸理学療法
対象疾患
肺炎・間質性肺炎・膿胸・肺がん・気胸等
病気や外傷にて呼吸器が障害された場合に対して、呼吸機能の回復・維持を目的に行います。
作業療法
当院では、各科医師の指示のもと、主に上肢の機能・認知・生活活動の向上を目標に以下の諸活動への働きかけを行います。
身体機能面への働きかけ
作業活動を通じて、実際の生活に必要な筋力、関節の動き、感覚機能などの維持・改善をはかると共にスムーズな動きや耐久性の獲得などを行います。
高次脳機能面への働きかけ
生活に必要な時間・物の扱い方・周囲の状況の認識、物事の記憶、計算、動作の順序や方法を決定し遂行していく等の能力を評価し、治療・訓練します。
心理面への働きかけ
長期入院や障害により失われ易い精神活動や生活に対する意欲の維持・改善をはかるとともに、不安を和らげ、共に活動します。
日常生活活動面への働きかけ
食事、更衣、排泄、などの身辺動作や家事動作に対して、その活動が出来ない原因を評価し、その人にあった適切なやり方・介助の方法を訓練・指導します。
職場復帰への働きかけ
職場復帰や就職に向けて、身体機能、作業能力、一般能力(学習能力、注意力、問題解決能力など)、移動、コミュニケーション能力などを評価し、訓練をします。
1. 脳血管疾患・神経疾患・内部疾患等による廃用症候群に対する作業療法
脳血管疾患対象疾患
脳出血、脳梗塞、脳挫傷、くも膜下出血、硬膜下出血、頭部挫傷など
神経疾患対象疾患
パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、末梢神経疾患など
廃用症候群
内部疾患、手術後の外科疾患など
安静臥床による二次障害を起こさないよう、医師の指示のもと、発症・手術後早期から安静度に応じて作業療法を開始します。
機能訓練
関節可動域運動や促通訓練、バランス練習を行うとともに、様々な道具(お手玉・ペグ・輪投げなど)等を用いて行います。
日常生活活動練習
対象者の方が送られてきた生活背景(日常生活・社会生活)を考慮し、直接的にまたは模擬的に日常生活動作や生活関連動作、趣味的な活動等へアプローチを行い、家庭や社会へ復帰できるよう援助を行います。また、必要に応じて自助具を利用した練習を行い自立への支援をします。
作業活動
対象者の状態にあわせた作業活動を取り入れ、壁面構成や手芸・工作を行います。
2. 整形・形成外科疾患に対する作業療法
対象疾患
鎖骨骨折、上腕骨頚部骨折、上腕骨顆部骨折、肘頭骨折、橈骨遠位端骨折、手根骨骨折、手指骨折など
腱板損傷、手指切断、熱傷、腱・靭帯損傷、末梢神経障害など
主として急性期の上肢の整形・形成外科疾患の患者さんに対して、発症直後の固定期からの患手管理指導、手術前後から必要に応じて作業療法を開始します。関節運動制限に対する関節可動域訓練、筋力トレーニング、物理療法を行います。
加えて、日常生活において使用できる手の機能回復を促すため、フォーム練習(にぎりやつまみ動作)や実生活を想定した手の使用訓練を行います。スプリント療法は、手の症状にあわせて装具を作製し、手の機能障害の保護や練習時に使用し、治療をします。
3. がん疾患に対する作業療法
運動、日常生活活動、ものづくり、介助方法指導や環境調整など、症状や精神的緩和を考慮し、病期にあわせて行います。
言語聴覚療法
小児
個人訓練
ことばの遅れ、発音が聞き取りにくい(構音障害)、吃音、難聴などの問題を持つお子さんへの指導・訓練を行っています。
また、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害の評価・指導も行い、保護者の方と今後の接し方や工夫を一緒に考えていきます。
地域連携
必要に応じて、保育園・幼稚園や学校、関係機関と連携して、お子さんを取り巻く生活環境の調整なども行います。
成人
言語・高次脳機能訓練
病気や事故で失語症、構音障害などのコミュニケーションの障害や高次脳機能障害を持った方への訓練や相談を行っています。また、吃音症に対しても訓練を実施しています。
言語訓練は、全体構造法(=JIST法 詳細はhttp://www.jist.org/ をご覧下さい)という訓練法を用いて、話し言葉中心の練習を行っています。徐々に、声が出たり、ことばが増えたり、なめらかに話せるようになったりと、改善される方が多いです。
入院だけでなく、外来でも対応しています。
嚥下訓練
脳卒中や、老化、肺炎、癌などによって、口、舌、喉などが上手く働かず、摂食・嚥下障害を引き起こすことがあります。食べるためのトレーニング、食事時の姿勢や飲み込み方法の指導、食物の形の調整などを行います。
さざなみ会
当院に通院しているコミュニケーション障害のある方と、そのご家族の「友の会」です。食事会などを通して交流をしています。
同じ悩みをかかえる仲間同士なので、気兼ねなく参加できます。(2020年より休止中)
小児リハビリテーション
小児理学療法とは
お座りが上手にできない・なかなか歩かないなど、運動の発達が心配なお子さんに対して身体の状態を評価しながら、発達を促す訓練を行っています。
また、まっすぐ姿勢を保てない、走れるけど転びやすいなど身体の使い方が不器用なお子さんに対する訓練も行っています。ボイタ法による訓練を受けることも可能です。
必要に応じて、ご家庭や通園・学校などで行う練習や援助方法の提案も行っています。補装具・車椅子・椅子など福祉機器の作製に対する相談もお受けします。
新生児集中治療室(NICU)に入院中のお子さんに対して、発達促進のためのケアやポジショニングなどの介入を行っています。

小児作業療法とは
発達の遅れや偏りのあるお子さんに対して、遊びを中心とした様々な作業活動を通してお子さんの発達を促します。
主には座る・立つ・バランスを取るなどの粗大運動の発達、つまむ・はなすなどの上肢機能の発達、食べる・着替えるなどの日常生活動作の向上、箸・鉛筆・はさみなどの道具操作の向上を目標に訓練を行っています。
保護者さんには必要に応じて介助方法の工夫やアドバイスをしています。
また、色や形の認識、大きさや方向などの認識、模倣課題など学習の基礎となる能力を向上していく訓練も行っています。
- 現在、小児作業療法は受け入れを休止しております。(令和6年7月~)

対象疾患
脳性麻痺、染色体異常、筋ジストロフィー症、精神運動発達遅滞、低出生体重児、
自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害、不器用、学習障害 等
リハビリテーションの受け方
リハビリは予約制になっております。リハビリをご希望の方は、最初に小児科の受診をお願いいたします。
地域連携
焼津市こども家庭センターや地域の関係機関と連携して、地域のお子さんの成長をサポートしていく活動を行っております。