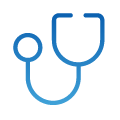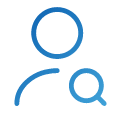腎臓内科
/ 診療科・部門
概要
診療紹介
腎臓内科では検診で指摘された尿検査の異常(血尿、たんぱく尿)の精査から糸球体腎炎、ネフローゼ症候群の診断・治療、慢性腎臓病の治療(食事指導、降圧療法)、糖尿病、膠原病など全身疾患に伴う腎臓病、電解質異常、二次性高血圧の診断・治療を行っています。
腎疾患は患者さんごとに病気の状態が異なるので、説明を充分に行い実行可能な治療を選択します。診断のために行う腎生検は4~5日、代表的な慢性糸球体腎炎であるIgA腎症のパルス療法は3~4日の入院で行っています。当科の治療目標は患者さんが将来的に透析療法に至らないことにしていますが、さらに心血管系の合併症発生予防、健康寿命の延長を考慮しています。
最近はかかりつけ医の先生に処方をお願いし、検査などは当院で行うことが増えています。
主な対象疾患
住民検診、職域検診で指摘された検尿異常(可能なら再検査後に受診してください)
かかりつけ医の先生の患者さんに発生する腎臓に関するあらゆる病態(日本腎臓学会の慢性腎臓病紹介基準を満たさなくても構いません)
- 慢性腎臓病
- 慢性糸球体腎炎
- 急速進行性腎炎
- ネフローゼ症候群
- 糖尿病関連腎臓病
- 急性腎障害
- 末期腎不全(血液透析療法、腹膜透析療法、腎移植の選択の説明も含む)
静岡県難病医療協力病院
| 疾患群 | 専門領域 | 担当医師名 |
|---|---|---|
| 免疫性疾患 | 膠原病系疾患一般
|
大浦 正晴 |
その他
慢性腎臓病(CKD)の病診連携
我が国では、約35万人が透析を受けていますが、年々その数は増加しています。当院腎臓内科では、かかりつけ医の皆さんと、慢性腎臓病(CKD)の病診連携を進めることで、透析導入患者を減らし、CKDが原因となる心血管疾患の発症を抑制したいと考えています。
受診時には患者さんに紹介状を持参させてください。必ずしも日本腎臓学会の慢性腎臓病の診断基準を満たさなくても構いません。
糖尿病性腎症の病診連携
糖尿病性腎症は透析導入患者の40%を占める上、腎症が出現後の進行が早い一方、治療により、微量アルブミン尿の消失、腎症の進行の抑制が可能です。そのため、早期からの病診連携により、生活指導の徹底、血糖や血圧の厳格な管理を行うことが大切と考えます。
診療科お役立ち情報「慢性腎臓病のはなし」
腎臓内科長 大浦 正晴
「慢性腎臓病(CKD)」について皆様に説明をさせていただきます。
この慢性腎臓病は有名になった「メタボリックシンドローム」より生命にかかわる合併症(脳卒中、心筋梗塞など)の発生リスクがワンランク高い疾患グループに位置しています。
- 腎臓の障害:蛋白尿を検出する(これがもっとも重要です)
血液検査、超音波検査、CTで腎臓に異常がある - 体から老廃物を出す腎臓の機能が60%以下である
以上が3ヶ月以上続く状態です。
この疾患が紹介され、以前より多くの方を私たちが診察させていただくにあたり、皆さんによりわかりやすく、行いやすい検査方法を現在外来で行っています。
- 1回の尿検査で腎臓の病気の勢いを示す尿蛋白の一日量を推定する検査。
(尿中蛋白/クレアチニン比の測定) - 1回の採血で腎臓の老廃物を出す機能を推定する検査。(eGFRの測定)
以上を用いて、慢性腎臓病の進行度をステージにわけ、標準的な治療を開始します。
尿検査は非常に多くの方々が行う検査です。
すべての方の尿検査の異常(腎臓内科では蛋白尿検出)を最初に総合病院で対応することは困難です。
日本腎臓学会ではかかりつけの先生が、総合病院へ紹介していただく慢性腎臓病の基準を作り、両者で相談して、日常の治療はできるだけかかりつけの先生にお願いするようにしています。尿検査で異常があったらまずお近くの先生にご相談ください。
医師紹介
-
関 常司 / せき じょうじ
-
役職
- 病院事業管理者
-
専門分野
- 腎臓病一般
-
資格
- 日本内科学会認定内科医
- 日本腎臓学会認定腎臓専門医・指導医
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
- 臨床研修指導医
-
-
菱田 明 / ひしだ あきら
-
役職
- 名誉院長
-
専門分野
- 腎臓病一般
-
資格
- 日本内科学会認定内科医
- 日本腎臓学会認定腎臓指導医
- 日本透析医学会認定透析専門医
-
-
大浦 正晴 / おおうら まさはる
-
役職
- 腎臓内科長 兼 膠原病・リウマチ内科長 兼 感染管理副室長 兼 血液浄化療法室長
-
専門分野
- 腎臓病一般
- 膠原病 高血圧
-
資格
- 日本透析医学会認定透析専門医
- 日本リウマチ学会認定リウマチ専門医
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- インフェクションコントロールドクター
- 日本化学療法学会認定抗菌化学療法認定医
- 結核病学会認定結核・抗酸菌症認定医
- 日本エイズ学会認定医
- 多発性嚢胞腎協会認定医
- 腎代替療法専門指導士
- 腎臓リハビリテーションガイドライン講習会修了
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
- 臨床研修指導医
- 日本内科学会認定JMECC修了
-
-
板谷 三紀子 / いたや みきこ
-
役職
- 副科長
-
専門分野
- 腎臓病一般
-
資格
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- 日本内科学会認定内科指導医
- 日本腎臓学会認定腎臓専門医
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
- 臨床研修指導医
-
-
森 瑞貴 / もり みずき
-
役職
- 医員
-
専門分野
- 腎臓病一般
-
資格
- 日本内科学会認定JMECC修了
- 日本救急医学会ICLSコース修了
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了者
-
外来担当医表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 |
1 | ー |
池谷 直樹 |
大浦 正晴 |
板谷 三紀子 |
大浦 正晴 |
| 2 | 大浦 正晴 | ー |
菊池 瑛世 (非常勤) |
ー | ー | |
| 3 | ー |
関 常司 |
ー | 大浦 正晴 | ー | |
| ー | ー |
糖尿病性腎症パス 板谷 三紀子 |
ー | ー | ||
| 午 後 |
ー | ー |
糖尿病性腎症パス |
膠原病リウマチ外来 | ー | |
| 大浦 正晴 (再診のみ) | ー | 大浦 正晴 (再診のみ) | 多発性のう胞腎外来 | 大浦 正晴 (再診のみ) | ||
- 受診には紹介状・予約が必要です
- 糖尿病性腎症パス外来・多発性のう胞腎外来は、他院から直接の紹介予約が必要です。
- 膠原病リウマチ外来も予約制です。初診時は紹介状が必要です。
休診情報
休診・代診はありません。
診療実績
2024年度実績
| 紹介初診患者 | 229名 |
|---|---|
| 血液透析導入 | 45名 |
| エコーガイド下経皮的腎生検 | 27例 |