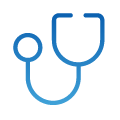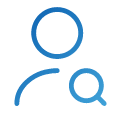中央放射線科
/ 診療科・部門
部門紹介
中央放射線科は各科からの依頼により、様々な検査と治療を行っています。
また、近年特に注目されている被曝問題に関しても、レントゲンや透視、CT検査等、放射線を用いる画像診断装置において被曝の低減に努めております。
放射線の影響
私達は自然の放射線を1年間に約2.4mSv浴びています。これの数十倍を浴びても障害は認められません。
放射線を少しずつ長い期間にわたって浴びた場合の影響は、同じ量の放射線を短い時間内に強く浴びた場合の影響に比べると、ずっと小さいことがわかっています。これは、人の体に備わっている回復作用のおかげです。
業務内容
一般撮影 (胸部、腹部あるいは骨の検査など)
X線検査(レントゲン)とはX線を利用して身体の部位を透視撮影する検査のことです。
検査時の注意事項
- 以下の物が撮影する範囲にある場合は外して撮影を行います。
持ち込めない金属類
ボタン、金属類、プリントのあるTシャツ、エレキバン、しっぷ、ブラジャー等
- 妊娠している方は医師、放射線技師に申し出てください。
乳腺撮影検査
乳房専用のX線撮影装置を使用して撮影する検査でマンモグラフィ検査とも呼ばれ、乳房を板で圧迫し薄くのばした状態で撮影を行います。触診ではわからない程の小さな腫瘤や微細な石灰化を画像としてとらえることができるため、乳がんの早期発見に役立ちます。
X線テレビ検査
胃透視
造影剤(バリウム)を飲んで食道、胃、十二指腸の形や粘膜の状態を見て病気があるのかないのかを調べる検査です。検査時間は約15分です。
注腸(大腸)造影
造影剤(バリウム)をお尻(肛門)から注入し、空気を入れ大腸を膨らませ直腸、S状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸まで撮影します。検査時間は約30分です。
CT検査
CT検査(Computed Tomography)はコンピューター断層撮影法の略であり、X線を使用し、体の断面を撮影する検査です。
撮影は体のあらゆる部位に対して可能であり、検査時間は5分~15分程度です。
体を構成している臓器(肝臓、腎臓、脳、肺など)や骨、脂肪などは、X線の通過しやすさ(度合)が少しずつ違います。
その度合をコンピューターで計算し、断面の画像を作成します。
MRI(磁気共鳴画像)検査
様々な角度から体の断面の画像を撮像することができます。
当院では、MRI装置3台(3.0T:1台、1.5T:2台)で検査を行っています。
検査時の事項
- MRI装置は強力な磁石を使用しています。その為、金属類を一切持ち込むことができません。
持ち込めない金属類
メガネ、時計、ヘアピン、アクセサリー類(ピアス、ネックレス等)、携帯電話、財布、鍵、磁気カード(キャッシュカード、テレホンカード等)、補聴器、入れ歯、湿布 など
- 以下の方はMRIを受けられない場合がありますので、担当医や技師にお知らせください。
ペースメーカーを装着されている方
体内に脳動脈クリップや人工関節等の金属を埋め込まれている方
妊婦の方、または妊娠の可能性のある方
閉所恐怖症などの狭い所が苦手な方
骨密度検査
骨密度測定は骨量測定とも呼ばれ、骨折を引き起こす要因となる骨粗鬆症のリスクを調べることができます。
当院の骨密度測定機器はDXA法(デキサ法)と呼ばれる微量なX線を利用して骨密度を測定します。
- 最も正確で信頼性の高いデータを得ることができます。
血管撮影検査
脳血管撮影
脳動脈瘤、脳動静脈奇形、動脈閉塞、動脈狭窄などの検索と治療(脳血管内手術)脳動脈瘤の検索では、両総経動脈、両椎骨動脈を、脳動静脈奇形では左右の内頚動脈、外頚動脈、椎骨動脈を選択的に造影します。
腹部・四肢造影
消化管出血、臓器出血、動脈閉塞などの検索。
悪性腫瘍などの検索。
肝臓などにある悪性腫瘍に対し、カテーテルで直接肝動脈から選択的に抗癌剤などを注入したり(TAI)ゼラチンスポンジなどでカテーテルで選択的に注入し出血部位などを塞栓させます(TAE)。
RI検査
RI検査はX線を使った検査とは違い装置からは放射線が出ません。患者さんの体内に入れた微量の放射線を測定しますので、検査時間に関係なく放射線を受ける量は同じです。
X線検査、CT検査、MRI検査、超音波等でも臓器の形はわかりますが、RI検査では機能や状態もわかるのが特徴です。
体外衝撃波結石破砕術
体外衝撃波結石破砕術(ESWL)とは、体外で発生させた衝撃波を、体を通して結石に集中させ、そのエネルギーで粉々に砕く治療法です。
細かく砕かれた結石は数日のうちに、おしっこと一緒に排石されます。
放射線治療
放射線治療とは、手術、化学療法(抗がん剤を用いた治療)と並ぶがんの3大治療法の1つで、身体や臓器を切除したりしないで放射線の照射によりがん細胞を消滅させたり、少なくする治療法です。放射線治療は単独で行うこともありますが、手術や化学療法と併用して治療を行うことが多くなっています。
放射線治療では、CT、および治療計画装置を使い、がんや周囲の正常組織の位置を正確に把握し、どの部位に、どの方向から、どのくらいの量を何回に分けて照射するかを検討し、治療計画を立てています。そのため、照射位置を正確に確認することは非常に重要となります。